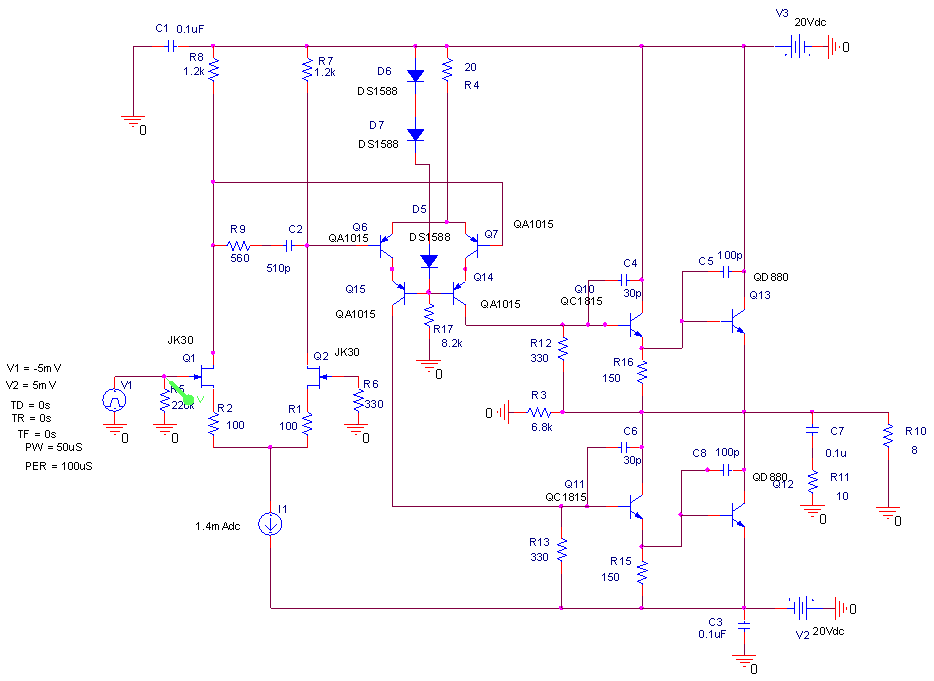
我が電池式完全対称型パワーアンプは最近その位相補正手法を改め、パワートランジスタのベータ遮断周波数による時定数を第1ポールにするなどという実に奇妙なアンプにしてしまった(^^;
その音はとても良さげなのだが、M−NAO氏情報では、どうもその方形波応答を見ると盛大にオーバーシュートが出るらしい。
音が良いのだから、まぁ良かろう(^^;、とも思うのだが、ちょっと気になることも事実。と言って手元に発振器がないのでリアルに確かめられない。
そこでこの際、またバーチャルにPSpiceで新方式の“電池式完全対称型パワーアンプ”の過渡解析をやってみようではないか。
という訳である。
さらに比較のために、旧方式、と言うかまっとうな方式で位相補正しているNo−139(もどき)その2もあわせてバーチャルに過渡解析する。
果たして、その間にはいかなる違いが生じているものなのか?
また、PSpiceシミュレータの能力は発振器とオシロスコープも不要としてしまうものなのか、も実に興味深い。
過渡解析というのは、「横軸を時間軸として電圧や電流などの変化を観測するもの」ということらしいが、過渡解析と言えばやはり方形波応答だ。
さっそく、電池式完全対称型パワーアンプのモデルに10KHzの方形波を入力して各部の応答状況を観る。
勿論NFBを掛けないオープンゲイン状態である。
オープンゲインは非常に大きいので、入力方形波の振幅は±5mVである。
実機でオープンゲインの状態で方形波応答試験などはできるものなのか? は、やったことがないので分からない。
まずは入力波形そのものを知る意味でも、入力のゲート抵抗R5(220KΩ)の上端に電圧プローブを取り付けて観測する。
その結果がこれである。
ぴったり+5mV、−5mVの10KHz方形波だ。軸にぴったり重なっているので見にくいが、それだけ立ち上がり立ち下がりに時間差のない全く理想的な方形波ということである。横軸にあるとおり、1サイクル100μSであるから、周波数は10KHzである。
次に、これが初段の負荷抵抗R7、R8、1.2KΩの両端においてどうなるか観る。
両方の1.2KΩの両端に電圧差プローブを取り付けて観測したのがこれ。
最初に+側に立ち上がるのがR8=入力信号側であり、−側となるのがR7=NFB側だが、その対称性は非常に良いし、信号の上下(プラスマイナス)の対象性も非常に良い。
差動アンプとはかように優れた対称性を発揮するものなのだ。
これで初段の電圧ゲインが計算できる。(814.3−810)/10=0.43倍=−7.33dbである。電圧ゲインは初段ではマイナスなのだ。こうなるのは、今やK式完全対称型パワーアンプでは旧タイプに属し、現代DCアンプの範疇には混ぜてもらえないのだろうなぁ(^^;
さて、その方形波応答だが、これで初段の段階で電圧の完全な立ち上がり下がりに4μS程度の遅れが生じてしまうことが分かる。
へ〜、そうなのか。ということは125KHz以上の方形波が入力されると立ち上がりが間に合わなくなるということになるが・・・
まぁ、そういうことなのだ。
では、なぜ初段の段階で電圧の立ち上がり下がりにこの時間遅れが生じるのだろうか。
その要因は初段に位相補正のために入れた560Ω+510pFではないか、ということでそれらを外して観測した結果がこれ。
なるほど。まさに時間遅れの要因は初段のドレイン間に入れた位相補正によるものであることが分かる。
当然だ。
他の避けがたい要素による時間遅れの影響を何とかするためにわざと時間遅れ要素を盛り込むのが位相補正であるからである。
さて、これを見ると微妙なリンギングが見られる。
のだが、これははるかMHz超の領域の要素によるものと思われる。がそれは何だろう? 2段目の入力容量の影響かも知れないが定かには分かるはずもない。
かえってそんな超高域の細かい要素まで計算して表示するPSpiceの能力には驚くばかり。
現実にもこうだとしたら、本当に発振器もオシロスコープも不要になりそう・・・。
次は、R12、R13、即ち2段目差動アンプの負荷抵抗=IV変換抵抗の両端における波形である。まあ、本当にIV変換抵抗と言えるのは終段がFETや真空管で構成されている場合で、トランジスタの場合は終段も電流入力で動作するので本来IV変換抵抗と言うのはおかしいのだが、まぁそれは置いておいて、波形はこのとおりだ。
ここでも差動の双方及び信号プラスマイナスの対称性は非常に良い。
が、細かくみると波形の上下で立ち上がり下がりの遅れ部分に微妙な違いがある。超高域要素だろうが確たる原因は分からない。
面白いのは、初段では立ち上がり下がりの遅れがリニアだったのに、ここでは振幅電圧が低い領域では遅れが僅少になって、振幅電圧の高い部分で余計に遅れるという状況になっていることだ。結局、この時点で最大振幅になるのに15uS程度の遅れが生じている。
何故こうなるのか? は、勿論私の分かるところではない(^^;
ところで、ここで2段目の電圧ゲインが計算できる。(1.365−1.171)/0.0043=45.1倍=33dbである。
次にダーリントンドライバー出力であるR15、R16の150Ω両端における波形を見る。
ここでも対称性は非常に良い。のだが、なかなかに面白い。
縦軸の電圧値を見ると分かるように電圧が減衰している。
のは、ダーリントンドライバーがいわゆるフォロア動作だから、ということなのだが、まあ、ここではそのドライバーTRのバイアス電圧0.6Vが差し引かれるから、と言った方がいいか(^^;
取りあえず計算するとダーリントンドライバーの電圧ゲインは (689−522)/194=0.86倍=−1.31dbである。
が、そんなことより注目すべきは、電圧の立ち上がりより、立ち下がりの方に初期段階で明確に多くの時間を要している、という事実だ。立ち上がり立ち下がりの非対称が明確なのだ。
この原因は分かる。ドライバーがシングルエミッタフォロアであるからだ。
シングルエミッタフォロアは信号の立ち上がりには能動的に対処できるが、立ち下がりには受動的にしか対応できない。と、K先生が25年前に「改訂版 最新オーディオDCアンプ」で解説されている。その結果がここでもこのとおりの現象となっているのだ。
が、それも結果としては4uS以内の時間領域でのことで、最大値に至るまでの時間はプラスマイナスで同程度におさまっているから、このアンプでは十分な応答速度範囲なのである。
では、最終的に出力端子ではどうなるのか、であるが、それがこれ。
出力の8Ωにおける波形である。
±5mVの10KHz方形波が、出力では±3.45Vの多少なまった10KHzの方形波になった訳だ。
これで終段パワートランジスタによる電圧ゲインは、6.9/0.167=41.32倍=32.32dbである、ということになる。
また、これでこのアンプのトータルオープンゲインも明らになって、3.45/0.005=690倍=56.8dbである。
初段からの合算でも、−7.33+33−1.31+32.32=56.68dbであるから、読みとり誤差を勘案すればピッタリである。
さて、最終的に終段の時間遅れ要素も加わり、結果、完全な立ち上がり立ち下がりには20uSの時間を要していることが分かる。
が、56.8dbもの電圧ゲインを得て、かつ無帰還で得られているこの波形は実に立派なものだ。と私には思える。
ところで、NFB回路で帰還電圧はこの20分1程度になるのだが、帰還電圧の波形自体はこの波形と相似形である。その帰還電圧が初段のNFB入力に加えられる訳であるから、NFBを掛けると、結果20uSまでオーバーシュートが生じるように思える。
どうだろうか?
と、さっそくNFBを掛けた状態で10KHzの方形波を入力し、8Ω負荷での出力波形を観る。
ただし、入力電圧振幅は±0.5Vと100倍大きくする。のはNFBが掛かってアンプのゲインがクローズドゲインの21.6倍≒26.7dbと大幅に小さくなるからである。
が、結果電源電圧±15Vではぎりぎり飽和するので、ここでは緊急避難で電源電圧を±20Vとする。
お〜!
確かにオーバーシュートとアンダーシュートは生じている。
定常時10.5Vに対し、ピークは15.5V程度だろうか。アンダーシュートはその反動で−0.5V程度だが、いわゆるリンギングは僅少だ。
が、この様な過渡応答状態になる時間は2uS程度のようだ。予想に反して短時間で収束している。結果的には嬉しいことだが、何故だろうか?
と、しばし考えた結果、その理由は、オープンゲインが大きければ、オープンゲイン時での2uS時点での立ち上がり電圧による帰還電圧で、所定のクローズドゲインのための帰還量になるから、ではなかろうか。
オープンゲイン時の最大振幅までの立ち上がりに要する時間遅れ=NFBの時間遅れではない、訳だ。
そうか。NFBを掛けるとアンプの動作が高速化(=周波数特性が広帯域化)するのは、こういう訳なのだ。
実は初段の位相補正を取り去ると、オーバーシュートが減少し波形再現性は非常に良くなるのである。
位相遅れ要素が少なくなるのだから当然のことなのだろうか。
が、この状態では良いのだが、他の構成要素が変動した際にアンプが発振する場合がある訳なので、残念だが使えないのだ。
では、100KHzの方形波を入力してみよう。
結果はこれ。
オーバーシュートとアンダーシュートの時間が長く、顕著になったように見えるが、実は横軸スケールを見ると分かるように、時間軸が10倍に拡大(=時間の進行を10倍スローモーションに)したから顕著になったように見えるだけで、その実質的内容は10KHzの場合と全く同じであることが分かる。
また初段の位相補正をなくして、同じく100KHzの方形波を入力してみる。
やはり、オーバーシュート、アンダーシュートとも大幅に減っている。
これで使えないのだからやはり残念ではある。
参考までに、1MHzの方形波入力。
予想されたとおりなのだが、やはり入力信号の立ち上がり立ち下がりに応答が間に合わない。
このため、方形波が三角波になってしまう。縦軸の電圧値を見れば分かるとおり当然ゲインも落ちている。
では、10KHz、100KHzの方形波入力でこんなオーバーシュートやアンダーシュートが生じ、1MHzの方形波入力では出力が三角波になってしまうアンプは、音楽再生用として妥当なのだろうか?
また、この様なオーバーシュートが生じないように対応策を講じなくて良いのか?
という点が問題である。
1MHzの方形波が三角波になってしまうのはやむを得ないとしても10KHz、100KHz入力であんなオーバーシュートが生じるのはどうも・・・、ではなかろうか。
と思えるのだが、実は問題はない。ようだ・・・(^^;
何故なら、音楽信号にはこんな方形波成分はないからだ。
また、ソースがCDであれば、もともとCDには20KHzの正弦波以上の高域成分は入っていない。
ま、そうは言えども試しに音声帯域の倍以上ということで、50KHzの正弦波を入力してその応答を観てみよう。
出力波形は、このように全く破綻のない綺麗な50KHz正弦波なのである。
十分ではないか。
この際、100KHzの正弦波も入力してみた。
う〜ん・・・、ピークを過ぎるあたりでちょっと波形が欠けている感じがあるかな。
これは高域の位相回転要素か位相補正手法によるもので、多分あの方形波応答にオーバーシュートが出ることと同要因かも知れない。
が、これがこのアンプの高域再生限界の現れでもないようである。
さらにNFB後の高域再生限界を探る。
500KHz正弦波の入出力波形。
入出力を縦軸スケール調整により対比して見れるようにした。ので良く分かる。
どうだろう。勿論左側がアンプ入力の原波形であり、0.1uS遅れて右側の波形がアンプ出力の波形である。
この辺がこのアンプの高域限界のようだ。
出力のピークは上の50KHz、100KHzの場合と同様に±11V得られているし、波形再現性も十分であるのだが、波形ピークの位置にむらが出始めている。
以上から、このアンプは1MHzは無理だが、500KHzまでなら大丈夫だ、ということになる。
我が“ヘッドフォンも鳴る電池式完全対称型パワーアンプ”、随分と広帯域なパワーアンプになってしまったものだ。
特異なポール配置とした我が電池式完全対称型パワーアンプでは、方形波入力においてオーバーシュートが発生することが分かったが、現実には実害(=TIM歪み?など)も生じていないことも分かった。
何故か?
は、すでに25年も前のK先生の単行本「改訂版 最新 オーディオDCアンプ」で明らかにされている。
そのTIM歪みの解説中に、NFBアンプでTIM歪みが生じないようにするには、「要するに高域のカットオフ周波数が一番低い部分より前のアンプのゲインが極端に大きくなく、ダイナミック・レンジが十分に確保されていればよい」のだ、と、明解に説明されている。
この電池式完全対称型は、初段電圧ゲインは上でみたように−7.33dbであるが、これは初段が飽和してTIM歪みが生じないようにするためのものでもあるのである。
な〜んて、偉そうに言ってみる(^^;
が、実は電流的に見るとぎりぎりセーフであったようだ。
NFBを掛けた状態で10KHzの方形波を入力し、初段の電流出力の状態を観ると・・・
これがNFBを掛けた場合の初段の実動作の姿なのだ。
差動アンプは入力側に加えられた原信号と、それがアンプ内で増幅処理されて出力からNFB回路を経由して戻ってきたNFB信号の差分を増幅するので、アンプ内部にある時定数によって位相回転が生じ、結果NFB帰還電圧に一瞬の遅れが生じる間、入力信号をまともに増幅する。
それが、このグラフの方形波立ち上がり時間(50uS間隔)におけるピークなのである。
このピークでアンプが飽和したりした場合にはTIM歪みが生じることがあり得る。ということなのである。
ピークは1.3mAに達しているが、このアンプの初段の動作電流値は0.7mA設定であるから、1.4mAまではOKなのである。
なんと余裕0.1mAで間に合っている状態だ。
もし初段の動作電流を0.1mA少なく設定していたらダイナミック・レンジが足りず結果TIM歪みが発生していた、ということなのかも知れない。
が、これはただそれだけのことだ。
現実に動作させる場合に、この様に立ち上がりの急な信号が入力されることなど考えられないのである。
500KHzの正弦波でも見事に通過しているのだ。
これ以上は、やってもただ単なる測定マニアの世界になってしまう。
続いて我がNo−139(もどき)その2である。
こちらの位相補正は2段目差動アンプの例の位置に入れたSEコン5pFで行っている。
5pFならほんの少量だ。
と思ったら大間違いで、実はミラー効果で実質10000pF程度の巨大容量になっているのである。
それが1.5KΩにパラとなって初段負荷としてぶら下がるのだ。その効果は甚大なのだ。
と、それがビジュアルにも理解できるシミュレーション結果がのっけから得られる。
上の場合と同様に、入力に10KHz、±5mVの方形波を入力し、アンプは無帰還状態で、まず、初段負荷抵抗であるR7、R8の1.5KΩの両端にける波形を観る。
結果がこれだ。
え〜〜!?
一見何がどうなっているのか分からないほどの波形だ。
が、よく見ると味わい深い(爆)
実質10000pF程度の位相補正コンデンサーが容量負荷となっているために、その充放電で結果電圧的にはこのような波形になるわけだ。
信号のプラスマイナスの対称性や差動の双方の対称性などを考えると非常に興味深い波形なのだが、深入りするほどの知識もないので深入りしない(^^;
多分、これで信号の位相が回転し、適切かつ効果的な位相補正効果が得られているのだろう、が、これで次のステージでは対称な波形が現れるのだろうか? と懸念しつつも先に進む。
ということで、次はR12、R13、即ち2段目差動アンプの負荷抵抗=IV変換抵抗330Ωの両端における波形である。
お〜!なんと言うことか!
取りあえず差動の双方と信号のプラスマイナスの対称性は確保されている。この点は初段負荷抵抗における波形からは信じがたいくらいだ。
また、方形波の立ち上がりはすっかり丸められているのも驚きだ。
実にinterestingな結果ではないか。
位相補正で位相回転が早まることとは即ち電圧波形的にはこのように立ち上がりがなまること。と、まあ当たり前のことなのだがこうも上手い具合に実現結果を見せられるとある種感動してしまう。
さらに、位相補正を行ったのは2段目差動アンプ入り口の片側だけなのに、その反対側もこれほど相似の波形が得られるのだ。頭では差動アンプだからそうなるはずだと思ってはいたが、ビジュアルに見るとやはりインパクトがある。
我が電池式完全対称型パワーアンプとNo−139(もどき)その2。位相補正手法の違いで随分と違った内部動作をしているわなぁ。
次は勿論ダーリントンドライバー出力であるR15、R16の150Ω両端における波形である。
すでに2段目入り口の位相補正で立ち上がり速度を緩められた波形になっているのだが、ここでも上の電池式の場合と同様波形の立ち下がり初期に時間を要している姿が明確に現れている。
シングルエミッタフォロアの非対称性だ。出力がシングルエミッタフォロアの場合、特に容量負荷がぶら下がると問題は大きいだろう。いにしえに、最初期のK式プリアンプの出力段はシングルエミッタフォロアだった。が、即プッシュプルエミッタフォロアに変更された。のはこれが理由だった。
が、ここでは許容範囲内だ。と思う(^^;
さて、結果として、最終的に出力端子ではどうなるのか、が、これである。
出力の8Ωにおける波形だ。
なるほどねぇ。2段目入り口で強力に位相補正を行ったために、その後ろにある時定数は最早殆ど陰が薄くなる、というか影響がないのだ。
2段目入り口の位相補正で拵えた波形が殆どそのまま出力の波形となる訳だ。
が、こんななまった波形をNFBで入力に戻したら、それこそ盛大なオーバーシュートが生じてしまうのではないだろうか?
と、さっそくNFBを掛けた状態で10KHzの方形波を入力し、8Ω負荷での出力波形を観る。
ただし、入力電圧振幅は±0.5Vと100倍大きくするのは、NFBが掛かってアンプのゲインがクローズドゲインの40倍=327dbと大幅に小さくなるから、なのは電池式の場合と同じ。
結果は・・・な〜んと!
ホントか!? と目を疑うほどに素晴らしい10KHzの方形波なのである。
オーバーシュートもアンダーシュートもない、理想的な出力波形ではないか。
と、これが2段目入り口で位相補正(=これは初段で位相補正を行うことである)を行ってこれを第1ポールにした場合と、それ以降、例えば上の電池式完全対称型パワーアンプのように終段入り口のポールを第1ポールとした場合の違いなのである。
1つは、NFBを掛けないオープンゲイン状態ではあれほど内部で方形波がなまってしまうのに、何故NFB後はこのようにごく正確な方形波出力が得られるのか? であるが、それは上でも書いたとおり、オープンゲインが大きければ、オープンゲイン時での1uSなり2uS時点での立ち上がり電圧で既にクローズドゲイン時の出力電圧に必要な出力電圧とNFBに回すべき帰還電圧が確保出来てしまうから、であろうか。
2つは、何故、ここではオーバーシュートが生じないで、電池式の方ではオーバーシュートが生じるのか? であるが、それは、139(もどき)その2が入力信号とNFB信号を比較する初段差動アンプに第1ポールを置いているからであり、電池式完全対称型はそうでないからである。
139(その2)のように2段目入り口=初段出口に第1ポールを形成すると、これまで波形解析で見たように初段差動アンプの出力において電圧波形の立ち上がりが既に大きくなまってしまう。すなわち電圧波形の立ち上がりのスピードが初段の段階で大幅に鈍化するので、それ以上の時定数しか分布していない2段目以降は完全にその電圧立ち上がりのスピードに付いていく。だから、出力まで殆ど初段で形成したままの電圧波形が伝達形成される訳だ。結果、NFB帰還電圧信号の波形もほぼ完璧に初段で形成した信号電圧波形どおりなる。初段の波形とNFB信号の波形が同じであればNFB後もオーバーシュートなど生じようもないのだ。
この点でこの2段目B−C間Cで行う位相補正手法は(上手くポール配置分散も図ることによって)、TIM歪みの観点からは、アンプ入力にローパスフィルターを入れて帯域制限した場合と同様の効果が得られるのである。(て、そうしたら10KHzの方形波として入力されないことになるのでもとより再現なんてことも出来なくなるのだが(^^;)
が、電池式では第1ポールが終段入り口である。だから初段の信号電圧形成スピードに対して終段入り口での時定数のために終段通過後のアンプ出力電圧=NFB帰還信号電圧の形成タイミングがどうしても遅れる。初段で形成した電圧波形がそのままでは出力まで伝達できないのだ。位相が回転して電圧的に見た場合そういう様相になるということなのだが、結果、信号電圧の立ち上がりの僅かな時間において初段の電圧の立ち上がりに対応する十分な帰還信号電圧が戻ってこない、ということになるのだ。そのために、オーバーシュートが生じてしまうのだ。
が、これで必ずTIM歪みが生じるか、というと必ずしもそうではないことは、上の電池式完全対称型パワーアンプのところでみたとおりだ。
2段目B−C間のCで位相補正すれば、あらゆる場合に方形波応答にオーバーシュートを生じることがないのか?、と言えばそうではないだろう。勿論第2ポール以降との適切なスタガー比を確保しなければならないはずだ。が、我が139(もどき)その2は完全対称型の連星効果のお陰もあって、適切なスタガー比が確保されているのだ。
かくして、NFB後の100KHz方形波応答もこうなるのである。
NFB前の内部動作においてあれほど信号波形がなまっていたことからはとても信じがたい波形再現性だ。
ゲインとNFBとは実に使いよう。なのだ。
といって、別に魔法ではないので、出来ないことは出来ない。
これは1MHzの方形波応答。
やはり入力信号の立ち上がり立ち下がりに応答が間に合わない。このため、方形波が三角波になってしまう。当然ゲインも落ちている。
という点は電池式の場合と同じである。
では、正弦波応答でどれくらいの帯域幅を有しているものか観てみよう。
これだけ100KHz方形波再現性が良いのだから、電池式より広帯域なのではなかろうか。とも思えるが・・・(^^;
50KHz
全く余裕だ。
100KHz
これも全く余裕だ。波形も実に綺麗な正弦波のままだ。この点では電池式よりも勝っているのではないか。
このようにK式完全対称型パワーアンプは別に新方式でなければ再生帯域が狭いという訳ではないので勘違いしてはいけない。
旧方式位相補正の139(もどき)であってももとより再生帯域幅は必要十分以上に広いのだ。
が、微妙な部分では電池式完全対称に比較して位相遅れが大きいことには注意が必要(^^;
というのも、500KHzの正弦波入力でこのアンプの高域再生限界が電池式完全対称型に叶わないことが明らかになるのだ。
一見して、電圧ピーク値が少し小さくなると共に、正弦波が三角波になってしまっているから、これは限界を超えている。
これは300KHzである。
これを見ると、No−139(もどき)その2の方の高域限界は300KHzと言ってよさそうだ。
以上、PSpice(評価版)で電池式完全対称型パワーアンプとNo−139(もどき)その2の過渡解析のまねごとをしてみた訳だが、それは即ち両者間の位相補正手法の違いを考えてみたということである。
結果は大きな違いといえば大きな違いであるし、大した違いではないといえば大した違いではないだろう。し、これで両者間に音の違いが生じる理由が明らかになったというものでもない。
が、多少は意味ありげなところもあったかも知れない・・・(^^;
なお、このシミュレーション結果及び我が拙い解析に妥当性があるのかどうかは当然全く保証の限りではない。ので、あしからず。
(2003年3月9日)